| |TOP|目次|サイト内検索はこちら |
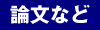 |
2011年5月29日(日)「しんぶん赤旗」
 (写真)『不破哲三時代の証言』(1500円) |
私は、1990年に書記局長に選任されて以来、不破さん(当時は委員長)とは、同じ党指導部を構成する一員として親身な指導と援助を受け、また数えきれないほどの相談をしながら、21年間にわたってともに活動してきました。言いつくせないほどの多くのものをこの大先輩から学んできましたが、つねに私が、感嘆の念とともに感じてきたことは、あらゆることにさいして、不屈の開拓の精神、あくなき探求の精神をもち、若々しい情熱を燃やしてのぞむ不破さんの革命家としての姿勢でした。
『時代の証言』(以下『証言』と略)では、たんたんとした語り口のなかから、革命家・不破哲三のこの姿を、全編にわたって読み取ることができると思います。本書を読み、私なりに、強い印象を受けたことを、率直につづってみたい、と思います。
著者は、1956年2月のソ連共産党大会で、「スターリン批判」がおこなわれたことから一つの結論を引き出したとのべています。それまで「絶対の権威」とされてきたスターリンの誤りを、不十分さや誤りをともないつつも、ソ連共産党自身が認めた。「私がそこから引き出した結論も、既成の『権威』に頼らず、マルクスやレーニンらの原点を自分の目で捉えなおしながら、日本や世界の革命論を研究しようということでした」(『証言』)。日本共産党が、1958年の第7回党大会で自主独立の路線を確立する2年前の決意でした。この決意が、その後の著者のすべての活動に終始一貫して貫かれていることが、『証言』からは生き生きと伝わってきます。
その最初の大仕事は、1964年に開始されるソ連共産党からの干渉、66年に開始される中国毛沢東派からの干渉という、二つの大国からの乱暴きわまる干渉攻撃にたいして、中央委員会政策委員会の一員として、相手の攻撃の「全論点を論破」する論陣をはることでした。その後も、「社会主義」を看板とした大国主義、覇権主義とのたたかいは、長く続きます。著者は、書記局長、委員長という重責を担って、たたかいの先頭にたつことになりますが、『証言』を読んで印象深いのは、著者がこのたたかいを通じて、ただたんに相手の無法を打ち破るだけでなく、党と自らを理論的にも、政治的にも鍛え上げ、日本と世界の運動への貢献となる記念碑的仕事をつぎつぎと残していることです。
たとえば、1979年末に起こったソ連のアフガニスタン侵略にさいして、わが党は、侵略の真相を動かすことができない事実をもって突き止め、ソ連を答弁不能に追い込みます。しかし、著者の批判の対象は、アフガン問題でのソ連の行動にとどまりません。「私は、ソ連の大国主義、覇権主義が世界の平和と諸国民の独立を脅かすこれだけの『巨悪』となった以上、その歴史を全面的に明らかにすることが急務になったと考えて、八一年の暮れから八二年正月にかけて、スターリン以来の歴史の解明にとりかかりました」(『証言』)。こうして世に送り出されたのが『スターリンと大国主義』(1982年3月、新日本新書)でした。この著作は、スターリンを「大国主義」に焦点をあてて根底から歴史的批判をくわえた、おそらく世界でもほとんど他に見られない著作となり、英訳されて海外からも反響が寄せられました。同書は、2007年に新装版(新日本出版社)として刊行されていますが、著者が、「新装版の刊行にあたって」で、「執筆から二十五年たったいま、この著作を読み返してみてうれしいことは、ここで展開したソ連大国主義をめぐる歴史的追跡において、基本的な訂正が必要だと思われる点が見当たらないことです」とのべていることは、たいへん印象的です。ソ連解体前の歴史的条件、制約された史料のもとでも、四半世紀の歴史の点検にたえる著作を生みだすところまで、著者の理論的探求は徹底したものだったのです。
1991年にソ連が解体し、クレムリンの奥深くに隠されていた多くの秘密文書が流れだし、野坂参三(当時、党名誉議長)がソ連で活動していた時代に同志を無実のスパイ容疑で密告していたという問題がもちあがりました。わが党は、事実を正確につかみ、本人にも問いただしたうえで、野坂を除名処分にしました。このときも著者の批判の対象は、「野坂問題」にとどまりませんでした。モスクワで入手したソ連共産党の内部文書の「雑然たる文書の山」を整理しながら、分析・追究をおこなうと、「そこには、野坂問題だけでなく、我々が知らなかったスターリンおよびその後継者たち、特にフルシチョフとブレジネフの時代の日本共産党に対する干渉活動の全容が、干渉者自身の言葉で実に生々しく浮かび上がってくる」(『証言』)。ここから生まれたのが、『日本共産党にたいする干渉と内通の記録――ソ連共産党秘密文書から』(1993年9月、新日本出版社)でした。著者は、「ソ連の大国主義、覇権主義の生身の全体像を、ソ連自身の文書で描き出した、そういう点では国際的意義を持つドキュメントになった」(『証言』)とのべていますが、ソ連覇権主義の醜悪な実態を、干渉者自身の資料によって、これだけ内面から系統的に明らかにし、それを通じて、この策動に正面から立ち向かい挫折と破たんに追い込んだたたかいの歴史的意義を解明した記録は、文字通り世界で他に例のないものだと思います。
アフガニスタン問題にせよ、「野坂問題」にせよ、反共派によって絶好の攻撃の材料とされた問題であり、わが党にとっては、この「逆風」を打ち破ることは当時の緊急の課題でした。ところが、著者は、「逆風」をただ打ち破るだけでなく、歴史と事実の全面的な究明をつうじて、今に生きる大きな財産をつぎつぎにつくりだしていった。この姿勢には、深く学ばされるものがあります。
「既成の『権威』に頼らず、原点を自分の目で捉えなおす」という著者の探求は、レーニンの理論の再検討にもおよびます。『証言』では、著者が、レーニンの積極的業績を高く評価しつつも、ときに現れる理論的弱点について、マルクス、エンゲルスという原点にたちかえって明らかにする努力をつづけたことがのべられています。とくにレーニンが、1917年、ロシア革命の最中に執筆した著作『国家と革命』――レーニンの著作のなかでも最高の地位を占める古典のなかの古典としてスターリン時代にいわば絶対化された著作――にたいして、大きくいって3回にわたって再検討にとりくみ、一つひとつ問題点を明らかにしていった足跡が明らかにされています。
1回目は、60年代後半の中国毛沢東派の干渉との闘争です。このとき干渉者たちが、「議会の多数を得ての革命」というわが党の綱領路線を非難し、マルクスの革命論を武力革命一本槍(やり)の革命と捻(ね)じ曲げるうえで、その「根拠」として振りかざしてきたのが『国家と革命』でした。著者は、「議会の多数を得ての革命」というわが党の綱領路線が、マルクスが追求した革命の大道の一つであることを歴史的に論証して毛沢東派の主張を徹底的にくつがえす仕事にとりくむとともに、そのなかでレーニンの『国家と革命』にたいしても、当時の文献的な制約のもとで、「一連の疑問の提起」をおこなったことを述べています。
2回目は、著者が、レーニン理論の全面的な吟味にとりくんだ『レーニンと「資本論」』(1997年〜2001年に雑誌掲載、新日本出版社から全7巻で刊行)です。「このレーニン研究では、もちろん『国家と革命』も重要な研究の対象となりました。革命論については、レーニンがマルクスのどこを読み誤ったのかの分析を含めて、私なりの理論的決算に到達しました」(『証言』)。著者はこの研究のなかで、レーニンが『国家と革命』のなかで展開した「強力革命必然論」は、マルクス、エンゲルスの国家論と合致するものではないこと、マルクス、エンゲルスは「議会の多数を得ての革命」という革命論を探求・発展させつづけたことを、古典家たちの「原点を自分の目で捉えなお」しながら綿密に解明していきます。ただ、「この段階では、(『国家と革命』で展開された)未来社会論の本格的な検討にまでは至らず、部分的な疑問点の提起にとどまりました」(『証言』)。私は、不破さんのこのレーニン研究が発表されたとき、長年胸のなかでつかえていたモヤモヤが一気に解消された興奮と感動を味わったことを思いだしますが、率直にいって著者がこの時点ですでに提起していた「部分的な疑問点」までは的確には読み取れませんでした。しかし著者のなかではなお解明すべき大きな課題が残っていたのです。
3回目は、2003年〜04年の党綱領改定のプロセスにおいてです。著者は、「マルクスの未来社会論を自分のものにし、その立場からレーニン理論や国際的定説を批判的に吟味する仕事」に「全力投球」でとりくみます。このなかで従来の「定説」とされてきた未来社会論が、レーニンの『国家と革命』に由来するものであること、それがマルクスの誤読にもとづくものであることが明らかにされ、マルクス、エンゲルスの本来の未来社会論の豊かな核心が再発見されていきます。こうした著者による理論的達成は、2004年の綱領改定における未来社会論の発展の決定的な土台となりました。
革命論の根本にかかわる問題を、「既成の『権威』に頼らず、原点を自分の目で捉えなおす」こと自体が、大きな勇気と努力を必要とすることだと思いますが、そうした探求をこの問題にかかわって40年余という長期にわたって持続しつづけてきた、あくなき情熱を傾けて探求しつづけてきたことは、さらに並大抵のことではなかったと思います。それをやりとげてきた著者の姿勢にも、私は深い敬意の気持ちをのべずにはいられません。
国政を舞台に、さらに世界を舞台にした、日本共産党を代表しての著者の活動にも、『証言』には、興味深い話がたくさん盛られています。
まず私が印象深く読んだのは、日本共産党が4議席から14議席に躍進した1969年に衆議院議員に初当選した著者が、国会論戦をどうやるか、その戦略戦術についても、自分の頭でつくりあげるしかなかったということです。「それまでは共産党は衆議院で四議席でしたから、質問時間は五分とか一〇分でした。論戦の戦略戦術も、あまり蓄積がないのです。こうなったら、質問の作戦も、現場を見ながら自分で考えるしかありません。私の出番は総括質疑(今の基本的質疑)の最終日だったので、初日から委員会に詰め切りで各党の質疑をずっと聞き、質問の仕方を勉強しながら準備しました」(『証言』)。
そういうところから出発しながら、予算委員会などを舞台にして、日本中をうならせた数々の名場面がつくられていきます。著者は自ら編み出した論戦の方法を振り返ってこう語っています。「質問のやり方は人によってさまざまですが、私は、聞くべき問題点の大筋は設定しますが、シナリオ的な筋書きはつくりません。相手側がどう出てくるかは、こちらからは決められませんから、どう出てきても反撃できるように、必要だと予想される資料はテーマごとに全部ノートに貼り込んでおきます」(『証言』)。
私は、1993年の総選挙で衆議院議員に初当選し、予算委員会総括質疑に立つことになりましたが、論戦の方法という点では、ずいぶん恵まれていたと思います。練達のお手本が目の前にありましたから。私が初質問をおこなううえで、最初の準備としてとりくんだのは、不破さんのそれまでの予算委員会の議事録をすべて読むことでした。不破さんからも直接、ずいぶんと質問法の助言をいただきました。
「質問の最後に何を聞くか、相手がどう答えても答えづらいような『切り口』を見つけることが大切なんだよ」
「相手の答弁の反論として『二の矢』、『三の矢』を使うときには、『強い矢』は一番後にとっておかなければならない。先に出してはいけない」
「単線のシナリオで質問を考えてはいけない。相手がどう出てきてもよいように、質問の主題に選んだ問題では、相手よりも『事に精通する』ことが大切だ」
こういうアドバイスですが、不破さんの質問議事録を読めば、そうした「質問戦の必勝の法則」が見事に貫かれていることが読み取れると思います。
『証言』にもどりますが、もう一つ、私が魅かれたのは、著者が国会で論戦の火花を散らした相手の「政治リーダー像」を、とても温かい語り口で回想していることです。とくに1970年代に著者と論戦をまじえた相手を、つぎのように描き出します。
「佐藤栄作首相はこの問題(創価学会・公明党による言論出版妨害事件)で、答弁を全部自分で引き受けました。……この問題は自分が責任を持って仕切る、という気迫が感じられ、それなりに感心しました」
「質問していて一番面白かったのは、田中角栄氏です。官僚を通さず、自分で仕切る実力を感じさせました」
「金丸さんは、最後はゼネコン政治の巨頭という悪名にまみれましたが、そこに至る道筋はどうであれ、ロランC基地返還の決断をしたことが、『功罪』の『功』の部分に属することは間違いないと思います」
「国会で実態を話したところ(大手電機企業の工場での過密労働の実態)、政府側もびっくりし、委員会室も静かになりました。大平さんはあとで顔を合わせたとき、『不破さん、あれは本当にあることですか』と真顔で聞いてきました」 「七〇年代の首相たちには、共産党の質問でも、大事だと思えば真剣に耳を傾け、対応する姿勢があったし、質問後も私の席に来て『今日はやられた』『あの質問はよかった』と感想を述べたりしたものです。最近の国会にはそうした雰囲気は感じられません」
こういう調子です。もちろん、一つひとつの質問戦は、そのどれもが国政の根本問題をめぐって正面からぶつかりあう真剣勝負そのものであり、著者の質問戦に相手は心底脅威をいだいたことでしょう。しかし、それに対して、相手も相手なりに真剣に答えようとする。そして、その姿勢には著者もまた温かい眼差(まなざ)しをそそぐ。そんな国会の雰囲気が伝わってきます。政治的立場を異にしても、人間として相手を尊重する。これはとても大切なことだと思います。そしておそらく著者のこの姿勢は、相手にも伝わり、日本共産党の値打ち(あるいは脅威)をさらに高めただろうと、私は思います。
「政治リーダー像」としては、著者が、その活動を世界に広げ、各国のリーダーたちの印象を語っているところにも、興味深いものがたくさんあります。
「ホー・チ・ミン主席の飛び入り発言は圧巻でした。……主席は、『我々が欲しいのはこういう援助です』と、開いた手を握りしめました。団結した力での援助が欲しい。問題の核心を表現した力強い握りこぶしでした」(1966年、ベトナム訪問)
「ハバナでの十一月の会談で、カストロ議長に直接、ソ連の行動(アフガニスタン侵略)を支持する真意を質しました。彼は、痛切な表情で『社会主義国として担う十字架だ』と答えました。キューバはそのとき、非同盟諸国会議の議長国でした。アフガニスタンはその加盟国だったのです。しかし、社会主義の国としては、ソ連を非難する立場に回るわけにはゆかない。そのつらい真情を『十字架』という言葉で表現したと受け取りました」(1984年、キューバ訪問)
「(カンボジアから)ハノイに戻って再びチュオン・チン政治局員と会談しました。主題は(ベトナム軍の)カンボジアからの撤退でした。複雑な問題をめぐるこのときの討論でも、彼の対応の誠実さには心を打たれました」(1984年、ベトナム訪問)
ここにも温かい眼差しを感じます。著者は、1998年に中国共産党との関係正常化を達成したのち、1999年から野党外交という新しい分野の開拓に乗り出しますが、この活動の発展を支えたのは、自主自立の精神を堅持しながら、相手の国の国情、それぞれの国のリーダーたちの立場を深く理解しようとする精神だったと思います。
「政治リーダー像」という点では、やはり宮本顕治さんを回想する著者の思いには、特別のものが込められています。『証言』では、2007年7月、宮本さんが98歳で亡くなったとき、著者が中央委員会を代表してのべた弔辞について述べています。「日本共産党員としての七六年間の宮本さんの活動のなかで、どこに光を当てるべきか、いろいろ考えました。行き着いたのは、日本共産党が存続の危機に立たされた危急の時期に、宮本さんが果たしたかけがえのない役割に焦点を当てよう、ということでした」(『証言』)。戦争中の獄中と法廷での闘争、50年代のスターリンの干渉と党分裂の時期の闘争、60年〜70年代のソ連と中国の両翼からの激しい干渉攻撃との闘争、この三つの時期に宮本さんが果たした役割、その功績を著者は語りました。私は、間近でそれを聞き、深い感動とともに、背すじをピンをのばされるような思いに包まれたことを思い出します。
私は、書記局長に選任された初期の数年間、宮本議長、不破委員長のもとで、活動した時期がありましたが、党史を切り開いてきた二人のリーダーとともに仕事をする機会に恵まれたことは、私にとってかけがえのない幸福であり財産だと考えています。
『証言』には、もちろん不破さん個人の歴史、精神史も語られています。その全体から浮かび上がってくる人間・不破哲三の姿も、魅力にあふれています。その魅力は実に多面的であり、どこに魅力を感じるかは、読む人それぞれだと思いますが、私が、とくに印象深く読んだ二つの点をのべたいと思います。
一つは、不破さんが、働く人たちの気分や感情、息づかいを、深く理解し、自らの心としてそれを代弁する国民的政治家に成長していく過程についてです。
『証言』では、不破さんが大学を卒業後、11年間にわたって鉄鋼労連の本部書記として働いた経験が、2カ月にわたるストライキ闘争に泊まり込みでともにたたかったことなども含めて、初めてまとまった形で語られています。不破さんは、「民間の労働組合運動と職場の状況、大企業の労資関係の現実に身近に触れたことは、貴重な体験となりました」とのべていますが、こうした経験は、後の国会質疑でのトヨタの「カンバン方式」の追及、ナショナル(現・パナソニック)の過密労働の追及や、労働問題と職場支部の発展のための新たな開拓的仕事をすすめるうえでも、大きな財産になったのではないでしょうか。
さらに、印象深いのは、1969年以来の旧東京6区の衆院候補者としての活動での苦労話です。「一番苦労したのは演説でした」。こう言われると、なんだかほっとする思いがしますが、不破さんが「私は喉が弱い」といっているのは、誤解だと思います。不破さんの声は、私の聞くところ、きれいなしかもきわめて良く通るテノールがかったバリトンで、決して通りが悪い声ではないのです。「喉が弱い」と感じておられるとすれば、おそらくその原因は喉ではなく、呼吸法のなかにあるのではないかと失礼ながら推察しています。
『証言』のなかで不破さんが、旧東京6区での活動を振り返って、下町の「情の深さ」とともに、「政治家として鍛えられました」と語っていることは、今日、わが党にとって重い意味をもつと思います。私は、最初の一回の体験(旧千葉1区)に終わりましたが、旧中選挙区制という制度は、有権者との関係でおのずと政治家を鍛え上げていくという面をもちました。いまの制度に改悪されたもとで、国民の気分や感情、働く人々の息づかいを深く理解する、大衆的政治家としてどう成長をはかるかという課題は、わが党の国会議員団のそれぞれに問われる重要な問題だと考えるものです。
もう一つは、近親の方々にたいする愛情が、行間からあふれるように感じられることです。生い立ちを語られたところで、さらりとした語り方ですが、お父さんの上田庄三郎さんについて語っているところは、とても印象的です。「学校が兵営でない限り、学校が牢獄でもない限り、子どもたちの最大の自由は認められ、最大の創造心を培う殿堂であらねばならない」「およそ子どもたちの自由と創造の天地と殿堂を壊し、これに圧迫を加えるものはもはや教育ではない」。民主教育の草分け、「上庄」さんの名文句を語る著者は、誇らしげです。私も、6年前に亡くなった父が小学校の教員をしており、その父が上田庄三郎さんについて、尊敬をこめて語っていたことを思い出し、とても懐かしい思いがします。
夫人の七加子さんへの想いは、もちろん特別です。不破さんが永年勤続議員として表彰を受けたさい、衆議院で9回の選挙戦を連続的に勝ち抜きその議席を四半世紀守り抜いたことを、みんなの力でやり抜いたと、後援会の主だった方々の前で話したときのことを、『証言』ではこう語っています。「みんなの顔を見ると、この間のあれこれが頭をよぎりました。妻は『口を開けば涙が出そうで』とあとで言っていました。それを察して、私は『いつも選挙では妻に代理を頼んでいるので、今日は妻の代理も兼ねて私が挨拶をします』という口上から報告を始めました。せめてもの『妻孝行』でした」。不破さんにとって、最大の理解者であり、「戦友」でもある夫人への深い想い、心づかいが、『証言』の全体から伝わってくるように、感じられます。
「私は、この新戦略の決定的な成否は、待望の『政権交代』が達成されたときに決まる、おそらくそのときが、自民党政治からの活路を国民的な規模で探究する新たな転換点になるだろうと、見定めていました」(『証言』)
ここで著者が「この新戦略」といっているのは、2003年以来の自民党を民主党が追う形での「二大政党づくり」の戦略のことですが、著者が「新たな転換点になるだろう」と「見定めて」いたことは、ほんとうに卓見だと思います。
『証言』では、1970年代以降の日本の政治史における「階級闘争の弁証法」が、その渦中でリーダーとしてたたかった人の目で、克明に語られています。日本共産党が前進・躍進をすれば、反動側は、新たな共産党封じの策略をもちだしてくる。その最も強烈な「逆風」となったのが、財界が主導してすすめた「二大政党づくり」の戦略でした。
「待望」の「政権交代」が実現したいま、まさに日本の政治は「自民党政治からの活路を国民的な規模で探究」する新たな局面に入っています。3月11日に発生した東日本大震災と福島原発事故は、戦後最悪の国難をつうじて、国民が真実の政治とは何かを考える新しい局面をつくりだしています。
私は、『証言』で著者が語っている「自民党政治からの活路を国民的な規模で探究する新たな転換点になるだろう」という一節を読みながら、著者が『マルクス、エンゲルス 革命論研究』(2010年、新日本出版社)で、エンゲルスの言葉を引きながら、政治の表面では、さまざまな逆行や困難があるように見えても、国民は「出来事そのものの展開」――その政治的な体験をつうじて、必ず「目覚め」をかちとっていく、そこにこそ歴史の「現実の推進力」があるとのべたことを、思い起こしています。
最後に、『証言』での著者の結びの言葉を紹介し、私も著者と未来への確信を共有しながら、多くの同志のみなさんとともにたたかう決意をのべたいと思います。
「政局的には、これからもいろいろな動き、新たな離合集散や政党の転変があり得るでしょう。しかし、政治が自民党政治の土俵に居座ったままでは日本の未来はないという現実は、今後ますます明らかになってくるでしょう。時間はかかっても、今日の閉塞状況の打開を求める国民の探究と、二つのしがらみ(『アメリカの傘』『財界依存』)から解放された日本の新しい進路を追求する私たちの努力が、大きく合流する時代が必ず来る、これが、時代の証言者としてこれまでの歩みを振り返ってきた私の確信です」
日本と世界にとっての文字通りの「時代の証言者」である不破哲三さんのこの著作が、よりよき未来を探求する多くの方々に読まれることを願ってやみません。
(しい・かずお 日本共産党委員長)